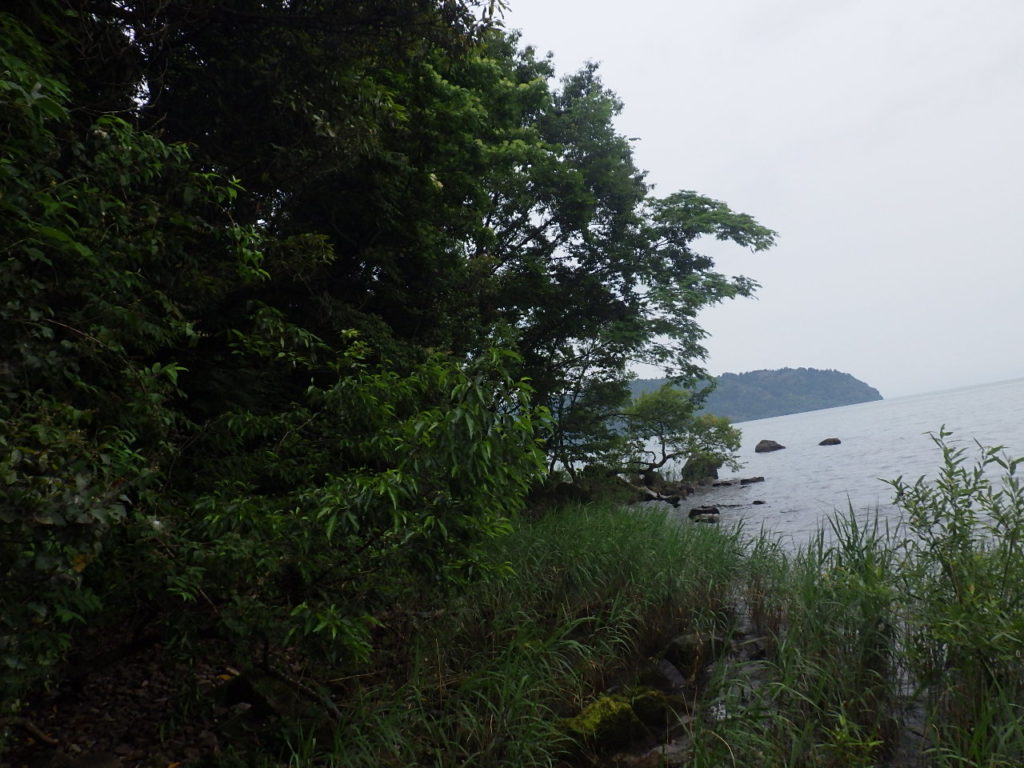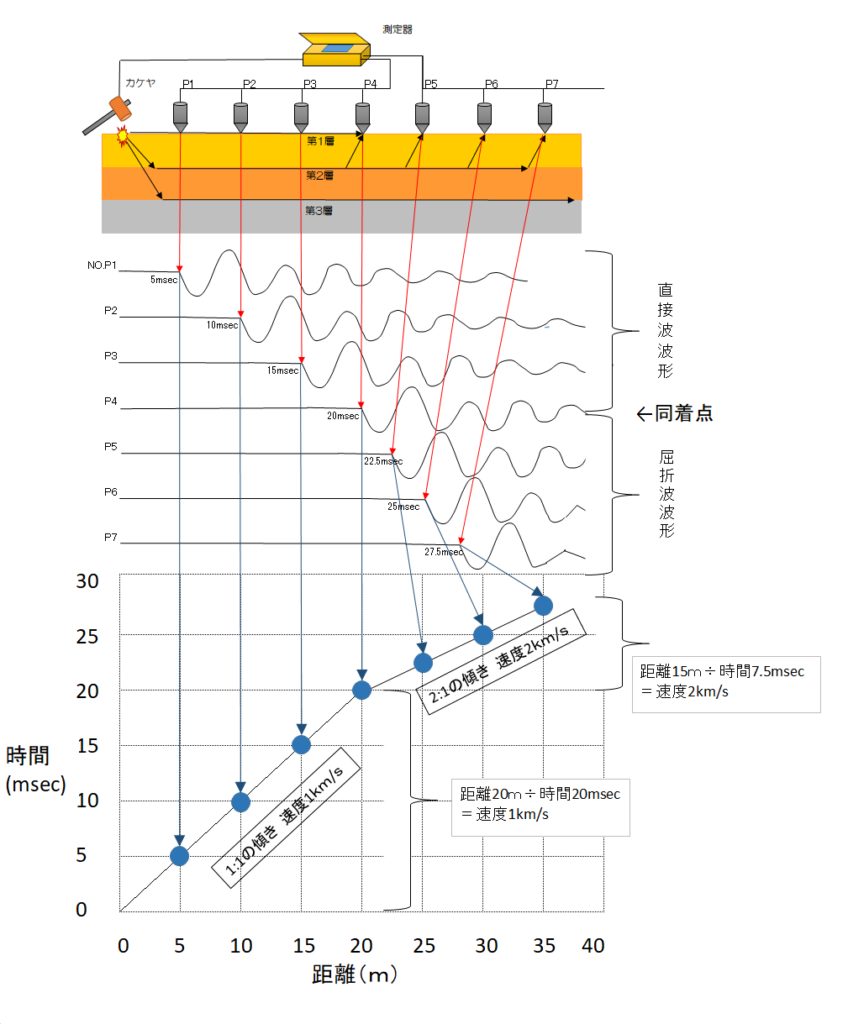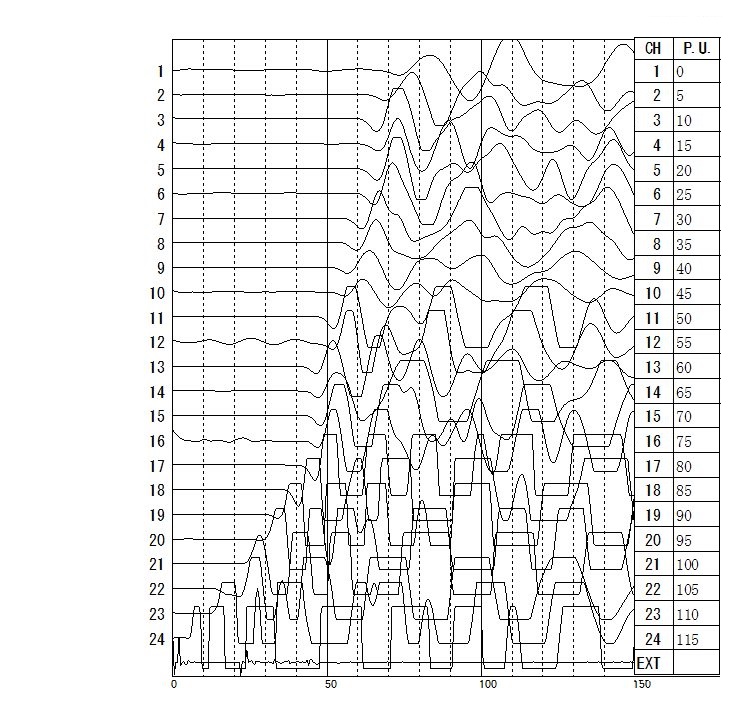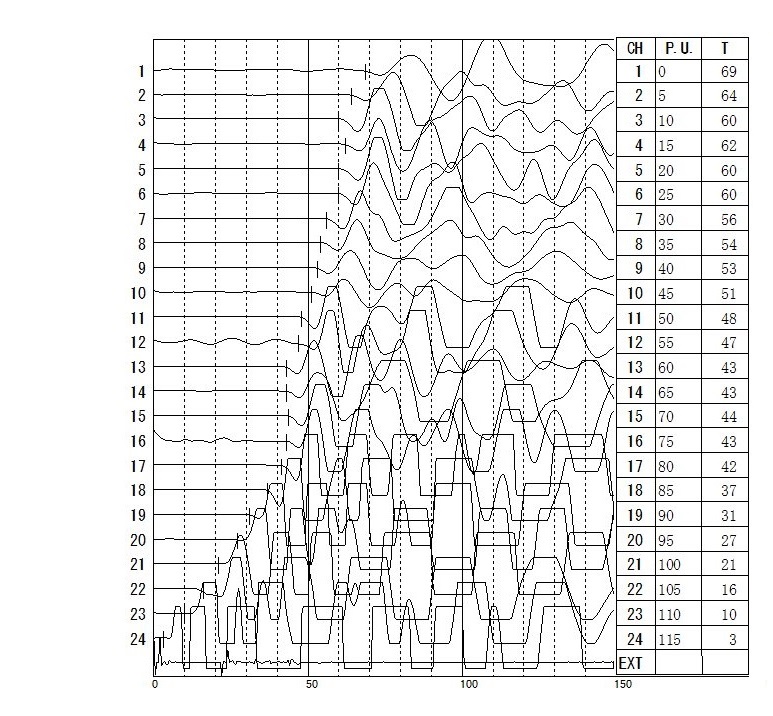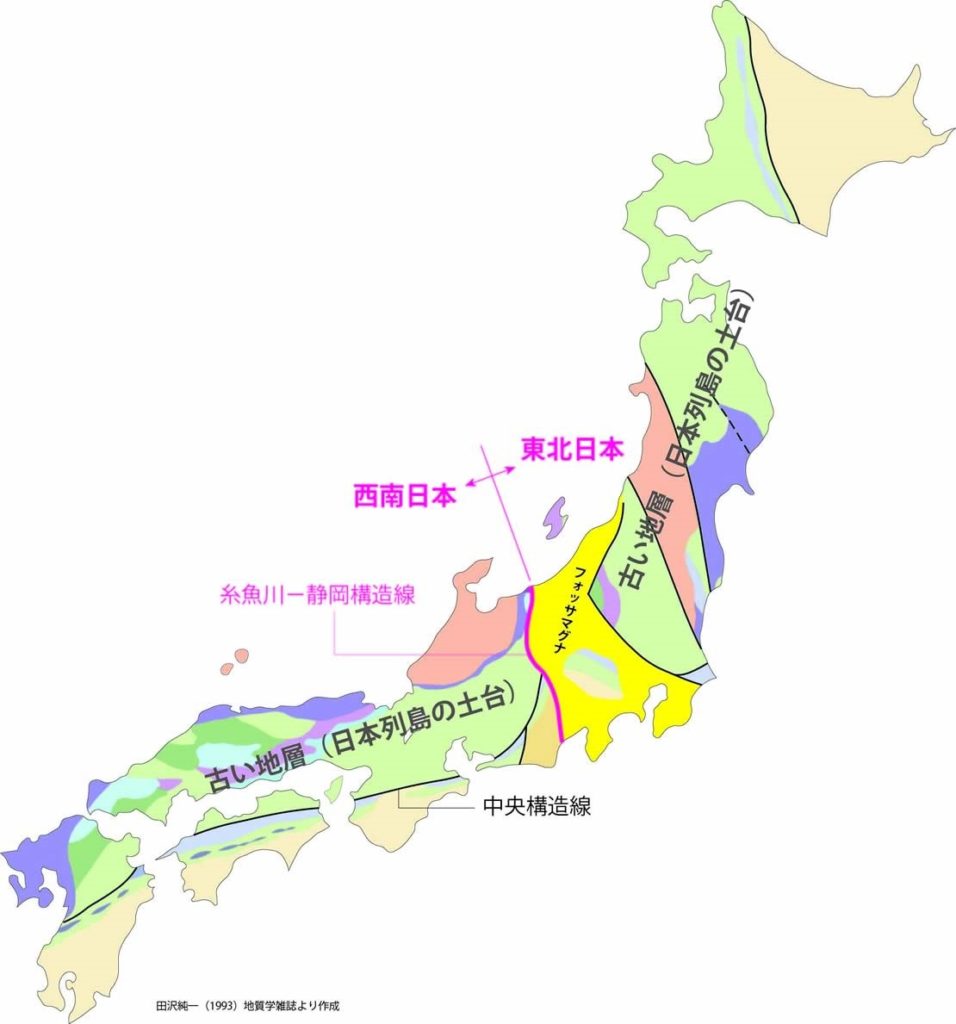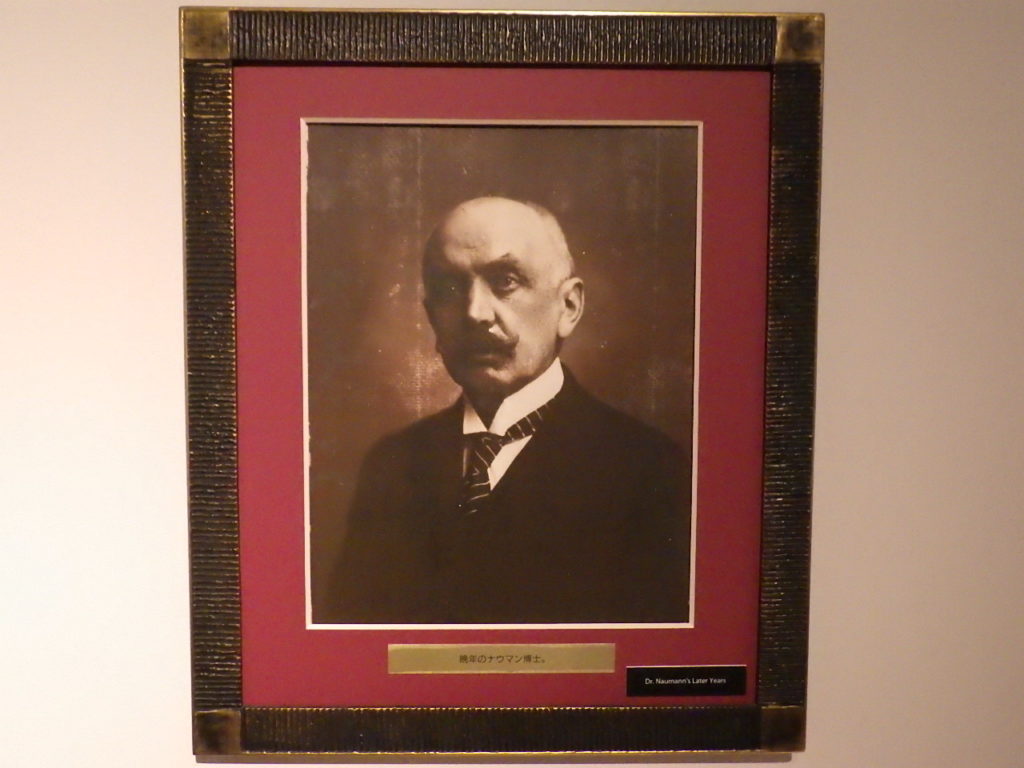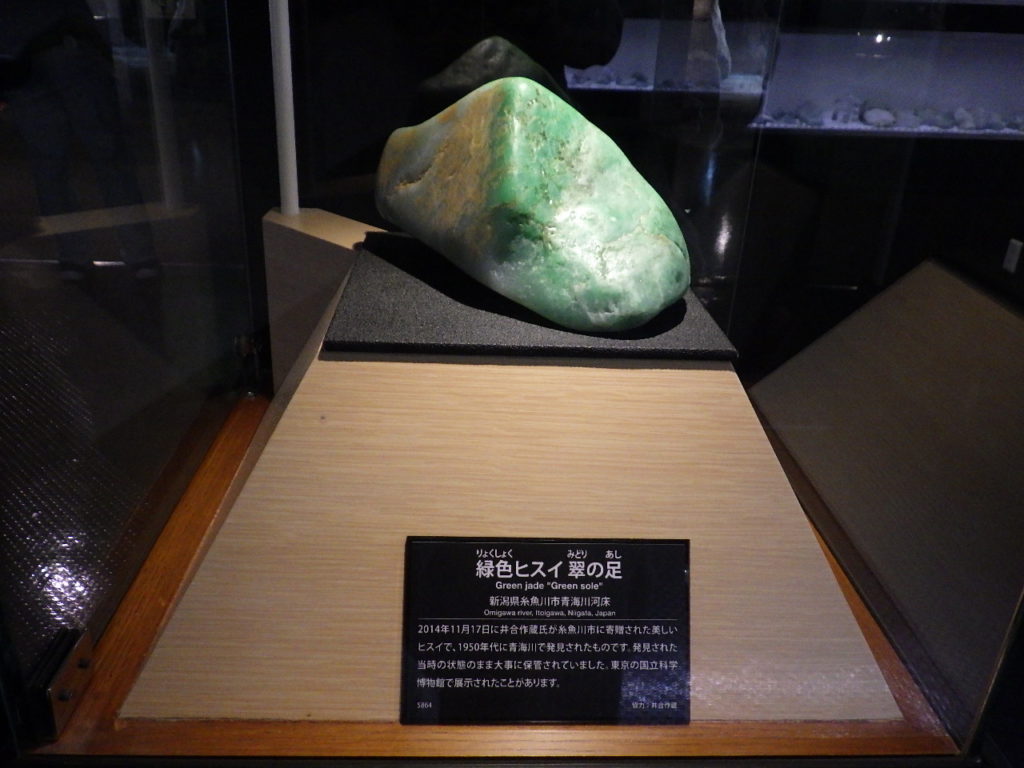News/Pickup
-

龍泉洞 岩手県岩泉町
現場の合間にプチ地質巡検。
岩手県の山間の国道をひた走ると日本三大鍾乳洞のひとつ龍泉洞が現れます。山口県の秋芳洞、高知県の龍河洞と並ぶ大洞窟です。
昭和13年に、ここに住んでいるコウモリとともに国の天然記念物に指定されています。
今なお調査が続けられる洞窟の全長は5,000m以上と推定されています。
最新の調査で確認された総延長は4,088m以上に及び、高低差は±195mに達しています。見学コースもけっこう昇降があり、暗いので足元が怖い!
私たちが現場の合間に行くということは、雨が降っている日ということなので、相変わらずの雨天。さらに平日の午前中だというのに観光客が多く、にぎわっていました。
見学コースには、鍾乳石は意外に少なく、豊富な地下水の滝つぼや清流などが見どころでした。




さらに別の日は、花巻の宮沢賢治記念館にも行きました。


-

天草 2025 社員旅行
今年の社員旅行は熊本県の天草地方へ。隠れキリシタン時代の教会などが残る歴史的な地方です。
現場でもあまり行ったことがなく馴染みが薄い。完全なしょ島地域というのは知らなかった。
あいにくの雨天だったが、熊本空港からレンタカーで昼食で調べていた「福伸」で食事。さすがに海鮮が美味でした。
昼食後、世界文化遺産に登録されている、崎津集落へ。


風雨が強くて外からゆっくりは見れなかった。崎津天主堂と崎津資料館みなと屋を見学。

ホテル・アレグリアで宴会
二日目、五和町のイルカマリンワールドから船でイルカウォッチング。海が荒れていてかなり揺れる・・・酔い止め薬が必要


イルカは本当に近くまで寄ってくる。感動。


昼食に車エビの踊り食い定食。天草四郎記念館を見学し、帰途につきました。
-

苗場山麓ジオパーク 石落とし 新潟県津南町
現場が無事終わり、周辺が苗場ジオパークが指定されている地域だったので巡検へ。
秘境の里・秋山郷を散策後、苗場溶岩流の露頭が壮大な岩屏風になっている【石落とし】を見学。

大規模な柱状節理が見事な景観。これが大量の雪解け水で剥離・落下するのが石落としと呼ばれるのだとか。
兵庫の玄武洞や北海道の層雲峡など柱状節理が有名な場所はいくつか見学したが、ここが一番スケールがでかいと感じました。

-

永源寺 滋賀県東近江市
令和6年度・第26期の地質巡検は、東近江市の永源寺地域周辺で実施しました。
滋賀と三重の県境にそびえる鈴鹿山脈に源を発した愛知川が、湖東平野に流れ出ようとしている所に臨済宗永源寺派の本山・永源寺があります。
このお寺は、1361年に佐々木六角氏頼が寂室禅師を招いて建設されました。
お寺の周辺や愛知川では、夏はキャンプ、BBQ、釣りなどで秋は紅葉を楽しむ人々でにぎわいます。
この地域の地質は、北から続いてきた湖東流紋岩の南端にあたり、永源寺はその湖東流紋岩の岩盤の上に建っています。
他に、比較的新しい古琵琶湖層や、花崗岩、花崗斑岩からなる古生層といった滋賀県を代表する岩石を見ることが出来ます。
また、愛知川沿いに集落を形成する河岸段丘崖や断層などの地質も観察します。


まずは永源寺の参道でみられる露頭を観察。谷部は護岸工事により見られなかったが、石段沿いは萱原溶結凝灰岩と呼ばれる流紋岩質の凝灰岩が切り立っており、苔むした石仏が鎮座しています。
次に、愛知川の河床に降り、古琵琶湖層の露頭を探索します。護岸工事で整備されていますが、草むらの奥に露頭がありました。


赤茶けた砂、シルト、灰色の粘土の層が水平に堆積しており崖を右へ追っていくと
地層が食い違っているのが見られ逆断層と考えられる。砂層にポツポツと穴が開いているのが見られたが透水性があるため
浸透した雨水が流れ出た後のように見られた。


道の駅・奥永源寺渓流の里で昼食後、角井断層へ。古い資料であり場所が不明瞭だが、県道を跨ぐ沢筋に分布する?
県道からそれて林道に入り、犬山花崗斑岩や秦荘石英斑岩を探す。資料には、異質岩片を含む萱原溶結凝灰岩も見られるとある。灰色の凝灰岩中に黒っぽい捕獲岩の類だろうか?


今回は、旧・永源寺町内を巡検しました。
目的の林道が封鎖されていたり、露頭が護岸工事されていたりと、資料に記されている状況と異なる箇所もありましたが、周辺でも同様の地質が観察できたことで、概ね目的を達成できたと思います。